アパート経営で失敗する人の10大原因と回避策|第三者のコンサルタントが解説

アパート経営は「相続税対策」や「安定収入の確保」として注目されています。しかし、実際に始めてみると「空室が埋まらず赤字になった」「返済が重荷になり生活が苦しくなった」といった失敗談も少なくありません。
近年は金融機関や不動産会社の提案によってアパート建築を検討する方が増えていますが、正しい知識や計画がないまま始めると失敗するリスクが高いのも事実です。 ここでは、アパート経営で失敗する典型的な原因とその回避策、さらに専門家がチームになることで解決した実例をご紹介します。
これからアパート経営を検討している方、あるいは既に始めていて不安を感じている方に役立つ内容をお届けします。
なぜ、アパート経営で失敗する人は多いのか?
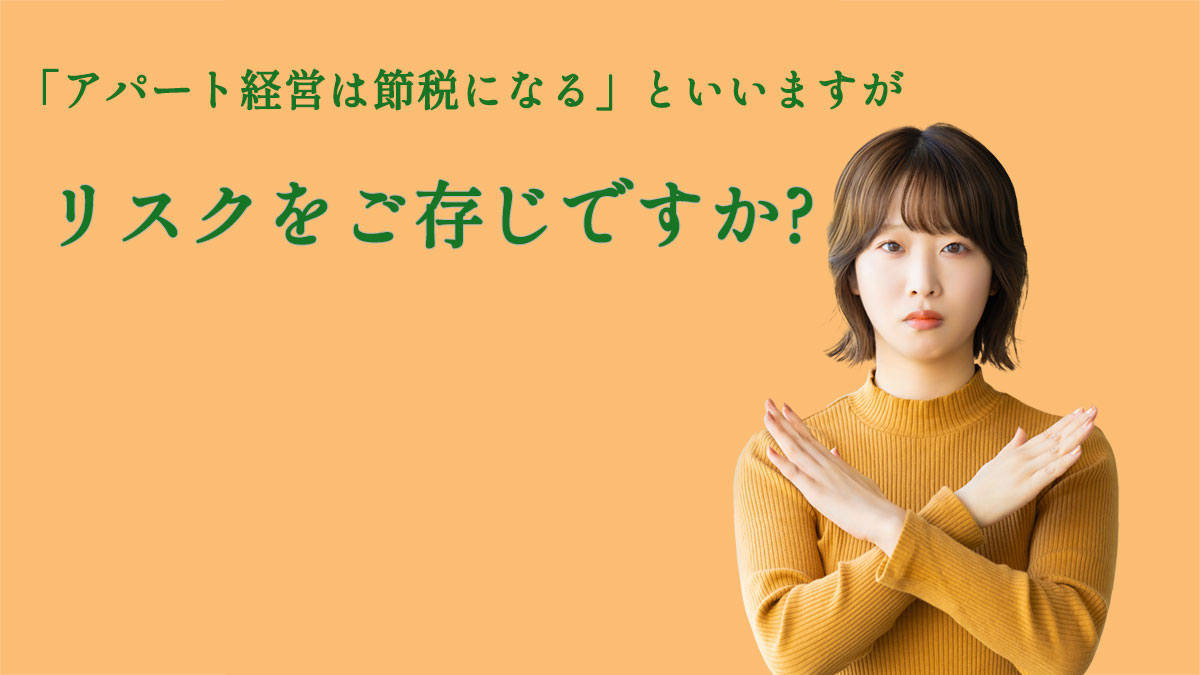
アパート経営は「節税になる」「不労所得が得られる」といったキャッチコピーで紹介されることが多く、メリットばかりが強調されがちです。その一方で、経営の難しさや長期的なリスクは軽視される傾向があります。
・人口減少に伴う賃貸需要の低下
・空室率の上昇
・金融機関の融資環境の変化
・相続税対策として建てたものの、節税効果が思ったほど出ない
こうした現実を知らないまま経営を始めると、赤字や相続トラブルに直面する可能性が高まります。
アパート経営失敗の10大原因
アパート経営で失敗する人が多い背景を理解したところで、次に「具体的にどのような失敗が起こりやすいのか」をみていきましょう。失敗の原因は一つではなく、立地・借入・空室・修繕・税金・出口戦略など複数の要素が絡み合っています。中には、経営を始める前の計画段階で防げるものも多いため、事前に知っておくことが何より大切です。 ここでは、実際の相談内容や事例でもよく見られる「アパート経営失敗の10大原因」を挙げ、それぞれのポイントを解説します。

1. 立地選定のミス
賃貸需要が乏しい場所に建てると、築浅でも空室が目立ちます。
特に都心から距離のあるエリアや、人口減少が進んでいる地域は要注意です。周辺に大学や工場があるから安心と思っても、数年後に移転してしまうケースもあります。将来の需要予測を怠ることが大きな失敗要因になります。

2. 過剰な借入・返済計画の甘さ
金融機関から「フルローン可能」と言われ、そのまま借入をすると返済比率が高くなりすぎます。
例えば、返済額が家賃収入の7割を超えると、空室が1室出ただけでも赤字に転落する危険性があります。また、低金利で契約したつもりでも、金利が上昇すれば返済額が膨らみます。借入は余裕を持った返済計画で組むことが鉄則です。

3. 空室リスクの過小評価
シミュレーションで「常に満室」を前提にするのは危険です。
近隣に新築マンションや人気のシェアハウスができれば、あっという間に入居者は流出します。
空室率10〜20%を見込んだ現実的な計画を立てることが不可欠です。

4. サブリース契約の落とし穴
「30年間家賃保証」と言われても、実際には契約後に家賃が減額されたり、契約自体が解約されることもあります。
サブリース会社の経営状況に左右されるため、安易に「保証」という言葉を信じるのは危険です。オーナーがリスクを負う可能性があることを理解したうえで契約内容を精査することが必要です。

5. 修繕・維持費の見積もり不足
築10年を超えると、外壁塗装や屋根補修、給排水設備の交換といった大規模修繕が必要になります。これらは数百万円〜数千万円におよぶ場合もあり、積立をしていなければ一気に資金繰りが悪化します。
修繕費を「いつ・いくら必要になるか」をしっかり事業計画に入れ込むことが、長期経営のカギです。

6. 利回り重視で本質を見失う
「利回り10%!」という広告は表面利回りで計算されていることが多く、実際には修繕費・管理費・税金を差し引いた実質利回りは5%未満というケースもあります。
高利回りをうたう物件ほど、立地条件や築古など裏があることも。数字の裏に隠れたリスクを見抜けないと失敗につながります。

7. 入居者トラブル・家賃滞納への備え不足
入居者同士の騒音トラブル、滞納はどの物件でも起こり得ます。保証会社を利用しない場合、家賃滞納はオーナーの収益に直撃します。
また、明け渡し訴訟などの法的対応に時間と費用がかかるケースもあり、トラブル対応の体制を整えておかないと大きな損失に直結します。

8. 出口戦略のない経営
アパート経営はゴールを設定しなければいけません。
「いつまで経営するのか」「売却するのか」「相続させるのか」を決めないまま進めると、築古物件を抱えたまま相続が発生し、家族間で揉めるケースも多いです。
出口戦略を持たないアパート経営は、資産どころか負債になる危険があります。

9. 税金面の誤解
アパートを建てれば相続税評価額は下がりますが、固定資産税・都市計画税・所得税など他の税負担は確実に増えます。
「節税できる」と思って始めても、実際にはキャッシュフローがマイナスになることも少なくありません。
総合的な税負担を理解しないまま建築すると、かえって家計を圧迫する結果になります。

10. 法制度・市場環境の変化
不動産投資は社会情勢や法制度の影響を強く受けます。
融資規制が強化されれば新たな借入は難しくなり、建築基準法が改正されれば建て替えや改修に大きな費用がかかります。
さらに、人口減少により地方や郊外では賃貸需要が縮小しています。
「今は大丈夫」でも将来の環境変化に備えていないと経営は立ち行かなくなります。
失敗しないためのチェックリスト

アパート経営で失敗しないためには、事前にどれだけ準備できるかが重要です。以下の5つを確認しておけば、典型的な失敗を防げる確率が大幅に上がります。
・人口動態、駅からの距離、周辺施設を調べる
・今だけでなく10年先の需要を見極めることがポイント
・空室率10〜20%、修繕費、税金を含めて試算
・表面利回りではなく実質利回りで判断する
・返済比率は家賃収入の30〜40%以内が目安
・金利上昇リスクも考慮し、無理のない借入額に設定
・管理手数料だけでなく、入居者募集力や対応品質をチェック
・空室対策やトラブル対応の実績を必ず確認
・家賃収入の1〜2割を修繕積立に回す
・空室や返済に備えて半年〜1年分の資金を確保
3つの成功事例からアパート経営のリスク対策を学ぶ
アパート経営はリスクがある一方で、事前に専門家へ相談することで失敗を避け、成功に結びつけたケースもあります。ここでは、当社に寄せられた相談事例を3つ紹介します。

事例1:空室リスクを回避し、安定経営を実現
ご相談いただいたのは、築年数の経過したアパートを相続されたオーナー様。
当初は「建替えをするしかない」と考えていましたが、立地や周辺需要を精査した結果、全面的な建替えよりも大規模リノベーション+管理体制の見直しを行うことで、初期投資を抑えながら入居率を改善しました。調査で分かったこと立地需要はまだ強い → 建替えではなく再生が有効実施した施策間取り改善、外観リノベ、管理会社変更結果入居率90%超を維持し、相続後も安定した収益基盤を確保ポイント:建替え以外の選択肢を検討することで、資金リスクを減らしながら収益改善に成功。
事例2:相続税対策をアパート建築から賃貸併用住宅へ切り替え
「相続税対策としてアパートを建てたい」というご相談でした。しかしシミュレーションの結果、アパート経営だけではキャッシュフローのリスクが大きいことが判明。
そこで当社は、自宅+賃貸併用住宅という形に切り替える提案を行いました。シミュレーション結果節税効果はあるが、空室リスクで赤字化の可能性提案した解決策賃貸併用住宅 → 節税効果を維持しながら自宅部分の利便性も確保結果相続税対策+自宅の快適性を両立し、家族全員が納得する形にポイント:相続税だけでなく、家族のライフスタイルと将来の相続分割まで見据えた選択が功を奏しました。
事例3:収益性と相続トラブル回避を両立
オーナー様が所有する土地は形状に難があり、「活用方法が分からない」とのご相談でした。当初はアパート建築を検討されていましたが、相続人間の分割リスクや空室リスクが懸念点に。
そこで当社は、土地の一部を活用した賃貸+残地を自宅利用というハイブリッド型の提案を行いました。課題土地形状が特殊で全面アパート活用は非効率提案した解決策部分的に賃貸活用し、残地は居住用に確保結果安定した収益を得つつ、将来の相続分割時にも揉めにくい形を実現ポイント:経済的メリットだけでなく、「家族の安心」まで含めたプランニングが成功の鍵となりました。
ここでご紹介した事例に共通するのは、「建てる」以外の選択肢を含めて検討できたことです。
不動産会社に行けば「売る」こと、建築会社は「建てる」ことを前提に提案する場合が多いですが、第三者機関である私たちは「建てる/建てない」「リノベ/賃貸併用/部分活用」と複数の可能性を提示し、オーナー様の資産状況と家族の将来を踏まえた最適解を導き出すことが可能です。
アパート経営のよくある質問4選

アパート経営については「相続税対策になると聞いたけど本当?」「空室が出たらどうなる?」など、多くの疑問や不安が寄せられます。
ここでは、実際のご相談や検索されやすいテーマから、特に多い質問をご紹介します。ご自身の状況に当てはめながら確認してみてください。
- アパート経営は相続税対策として必ず有効ですか?
-
節税効果が出るケースもありますが「必ず」ではありません。
アパートを建てると「貸家建付地評価」や「借家権割合」で相続税評価が下がります。ただし、空室が多いと評価減が小さくなり、期待したほどの効果が得られないこともあります。
さらに、固定資産税や所得税が増えるため、相続税だけに注目すると逆に負担が増えるケースもあるのです。検討段階でしっかりと事業計画を確認することが大切です。 - 空室率はどのくらい見込むべきですか?
-
最低でも10〜20%は見込んでシミュレーションすべきです。
「満室想定」で計算するのは危険です。周辺の賃貸需要や空室率を調査し、現実的に見積もる必要があります。特に東京23区でもエリアごとの差が大きく、駅近・大学病院近くなら低リスクですが、郊外や競合が多いエリアでは20%以上の空室率を見込むケースも少なくありません。 - 表面利回りと実質利回りの違いは?
-
表面利回りは“目安”、実質利回りが“現実の収益”です。
表面利回り=年間家賃収入÷建築費で計算されますが、これには修繕費や空室リスク、税金は含まれません。
一方、実質利回りはそれらを差し引いた「実際の手取り」を示します。
投資判断をする際は必ず実質利回りで5%以上を確保できるかを基準にするのが望ましいです。 - サブリース契約は安全ですか?
-
契約内容次第です。
「30年間家賃保証」といっても、途中で家賃が減額されたり、契約が解約される可能性があります。一見安心に見えますが、サブリース会社の経営状況に左右されるためリスクゼロではありません。
契約書の「家賃減額条項」や「解約条件」を必ず確認し、可能なら第三者にチェックしてもらうことをおすすめします。
中立・独立の立場から見た「アパート経営失敗」を防ぐ方法

多くの不動産会社や建築会社は「売れば・建てれば節税できます」と勧めますが、私たちネクスト・アイズは中立・独立の立場から助言するため、「建てない方が良い」という判断も率直にお伝えします。
例えば、世田谷区の地主様から「相続税対策でアパート建築を検討している」と相談を受けました。詳細にシミュレーションした結果、賃貸併用住宅に切り替えることで、相続税の負担を抑えつつ将来の相続トラブルも回避できました。
当社の強みは、税理士・建築士・不動産コンサルタントがチームで連携していることです。
そのため、
・相続税対策として本当にアパートが有効かどうかの シミュレーション
・建築・リノベ・売却など複数のプランを比較する 活用方法の提案
・空室率や修繕費を加味した 収支計画の作成・ご提案
・相続人間の争いを防ぐための 分割・承継も含めたご提案
こうした検証を通じて、「建てる/建てない」の二択に縛られず、ご家族の資産と将来を守る最適な方法を一緒に考えることができます。
アパート経営は「節税」「安定収入」というメリットもありますが、安易に始めると失敗リスクが非常に大きい投資です。成功の鍵は、立地選定・現実的な収支計画・出口戦略・専門家のサポートです。
ネクスト・アイズでは、相続・不動産・建築に強い専門家チームが中立の立場から「本当に建てるべきかどうか」まで含めて、最適な解決策をご提案しています。





